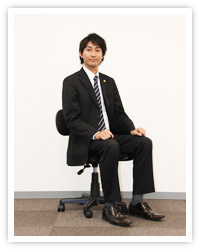最高検察庁から全国の高等検察庁、地方検察長に対し、在宅のまま捜査する事件のうち、起訴が見込まれ供述が立証上重要なものや、取り調べの状況をめぐって争いが生じる可能性があるものについて録音・録画を試行するよう通知がされたようです。
取り調べの録音・録画は、身柄拘束されている事件、つまり逮捕、勾留されている事件について行われていましたが、この対象を拡大するということです。
取り調べは、密室で行われるため、警察官や検察官による威圧的な取り調べやミスリーディングな取り調べにより誤った内容の供述調書が作成されることがありました。
これが冤罪の原因となっているということで、取り調べの録音・録画が法律により義務付けられましたが、その対象は身柄拘束されている事件に限定されていました。
その後も、警察官や検察官による不適切な取り調べが相次いだことを受けて、在宅事件にも対象を拡大するに至ったようです。
取り調べの録音・録画がされていてもなお、不適切な取り調べが行われており、今回の拡大を受けてもなお、不適切な取り調べが完全になくなるとは思いませんが、一定数、減少することは期待できるのではないかと思います。
弁護士としては少しでも冤罪が少なくなればと思います。